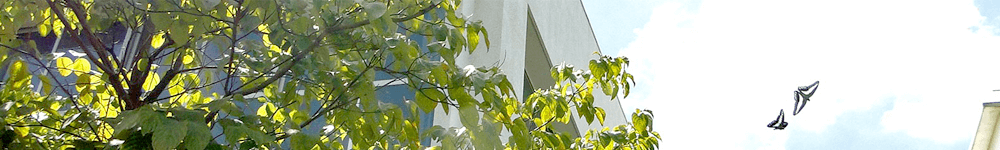こぼれ話
こぼれ話New
その554 のれん 2026.2.5
2026/02/05
街のそば屋や居酒屋では、「営業中」の印にのれんを出し、
営業時間が終わるとのれんを引っ込める。
もう一軒と思って店の前まで行ってのれんが出ていないとがっかりするものだ。
広辞苑では、のれんは
「もと禅家で冬の隙間風を防ぐために用いた垂れ幕」とある。
そのような垂れ幕で隙間風が防げるものだろうか。
古語辞典には「のうれん」の見出し語があり、
「もと禅家で、すだれの隙間をおおったもの」とあった。
確かに漢字で暖簾と書く。
隙間風もおだやかになりそうだ。
柳家さん喬師匠の「ねず穴」という落語を見た。
田舎で農業をする兄弟がいた。
兄は田畑の半分を弟に譲って江戸へ出て商売を始め、がんばって店を大きくした。
弟は残った田畑で生活していたが、遊びを覚えてしまう。
借金で首が回らなくなって兄の店で奉公したい、と江戸の店を訪ねてきた。
兄は、弟を雇えば他の奉公人と同じようには扱えないと思う。
心を鬼にして「三文の銭をくれてやる、これで商売を打て」と追い返す。
恨んだ弟は「きっと見返してやる。」と一本の藁を仕入れることから商売を始める。
朝から晩まで働いて、店を構えて奉公人も雇うようになった弟はある日、番頭に言う。
「兄さの所へ行こうと思う。
兄さは何でも持ってるから、
土産にはいくらか包んでうまい物でも食ってもらいたい。
いくらがええか。」
「三両ほどでいかがでしょう。」
「三両もか。」
「店ののれんということもあります。
蔵が三つもあるこの店ですから、三両で釣り合いましょう。」
「そうか。その三両と別に三文、包んどくれ。」
兄の店を訪ね、元手の三文と土産の三両を渡して打ち解けた二人。
酒を酌み交わして枕を並べて寝ていると、
ジャーン、ジャーンと半鐘の音。弟の店の方角の火事だ。
と話は続く。
広辞苑「のれん」の4には、
「店の格式や信用、永年の営業から生ずる無形の経済的利益」とある。
会社が他の企業を買収する時、
その企業の信用度を評価して「のれん」として計上するのだそうで、
のれんという古くからの言葉が、現代の経済用語で使われている。
逆に信用度が低いとマイナスの「のれん」を計上することもあるそうだ。
弟の店はすべて焼けてしまう。
蔵の漆喰にあった鼠穴から火の粉が入ったのだ。
焼け出された弟は、兄に借金を申し入れるが冷たくあしらわれ、、、
というのは夢で。
「火事は燃え盛るというて、
その夢を見たおめえの商売はもっともっと大きくなるぞ。
だども夢を見るのは五臓の疲れというぞ。
弟よ、おまえ、どっか悪いんでないか。」
「いいや、夢は土蔵の疲れだ。」
という落ち。
いらっしゃる方にはのれんを高く掲げて入りやすく、隙間風はないようにお迎えしたい。
「次は半鐘を売るか。」
「やめとけ、おジャンになるから。」
それじゃ火炎太鼓だよ。